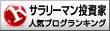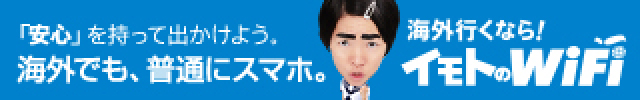【ロジカルシンキング】話し合いをスムーズに進めるコツについて【演繹法】
皆さまこんにちは
会社からブログ主君いくー?と言われ、会社の金で自己研鑽ができるんだからいきます!と研修内容も良く聞かず即答で受講希望をしました。が、今の所良い判断だったと思います。業界他社/異業種の方と立場を越えて議論する事も面白いですし、講義内容も目から鱗状態です。ただ相変らず名前と顔が一致しません。。
正直まだまだ研修で学んだことをインプットすらできていない状況ですが、アウトプットする為に、ここで皆様には犠牲にご紹介したいと思います。尚、笑い的なおもしろさは皆無なうえ、長いです。
以下内容は全てわたしがアウトプット用に勝手に作ったもので、実際の研修での事例やシチュエーションとは全く異なります点、ご承知おき下さい。またこれが正しい考え方、というわけでもありません。
結論として
・議論を行う双方が前提条件のすり合わせを行う事で議論の内容や論点から横道にそれることを減らすことができる。
・論点や問題点について、深堀をおこなう。条件や状態を具体化させることで、議論すべき内容を明確にし論点に沿った議論を行うように誘導させる事ができる。
という事をテーマとしています。では、前提条件とはなにか?事例を上げながら説明したいと思います。
衣料店の悩み
問い:
とある衣料店が【ピークタイム中に店舗内が汚くて購買意欲が下がる】とクレームを受けており、悩んでいる。どういった改善案があるのか、グループ内で議論し最適とおもわれる結論を出しましょう(5分間)。
答え:たくさんあります。みなさまならどう考えるでしょうか?1分程度思い浮かべて頂けますと幸いです。
グループワークのサンプル:
回答者:
グーループメンバーは3人で、偶然にもアパレル関連に従事していた為、日頃の経験を踏まえ意見を出し合います(以下Aの人、Bの人、Cの人)
3人の意見:
Aの人→ 手直しの回数を増やす。製品を素早く畳むための教育を行う、売場ラウンドを徹底させることで陳列の乱れを無くす。
Bの人→ 店舗設備やクリンリネスの慣行、ピークタイムに対応できるよう通路を広くする。売場に段ボール等が置きっぱなしにならないようにする。ピークタイム中にタイムセールを行う事でお客さん心理を改善させる。
Cの人→ 子供が触るおもちゃのコーナーは重点的に手直しする。店舗設備やクリンリネスの慣行、老朽化した設備を新しいものにすることで綺麗なイメージを与えるようにする(試着室/レジ台/トイレ)。
同業他社の3人がクレーム対してどういう改善をすればよいかと意見を出し合いますが、とりわけAの人が商品の乱れに対し、対策案を熱く語ります。
BとCの人はその熱い持論に圧倒されとりあえず相槌を打ちますが、それってそんなに問題かな?と心の中では思っています。Aの人も、持論を必死に説明しますが、あまり食いつかない2人に対し、納得がいかない様子。
どうすればいい、という結論に中々達する事ができず、あーでもない、こーでもないと時間だけが過ぎていき、お店の愚痴や売上の話が出たり途中脱線しつつも、しょうがないからとりあえずの結論を出しました。
なぜこのようなことになるのでしょうか?
原因は、2つあると考えます。
1. 双方の前提条件(一般常識/ルール)をまずはっきりさせ議論を展開させていないから。
2. 問題に対する背景が深堀りされず議論されているから。
1. 双方の前提条件(一般常識/ルール)をまずはっきりさせ議論を展開させていないから。
Aの人と、Bの人、Cの人は同業ですが、実は大きく異なる前提(一般ルール)部分がありました。それは
商品の陳列方法が違う、という前提があることです。
Bの人、Cの店舗は8割方ハンガーに服を掛けて陳列を行います。ハンガー掛けされた状態で納品された商品を一度品出しをしてしまえば陳列が乱れる事は少ない。それが前提条件です。
一方で、Aの人の店舗は、平台やゴンドラ(スーパーとかでよく見かける商品を置く棚)に商品をたたみサイズ毎に綺麗に敷き詰めて陳列を行います。
お客さんは服を広げて、適当に畳み、棚に戻します。ひどいときはくしゃくしゃ、っとして棚に押し込みます。Aさんはお客さんが散らかした服を必死にたたんで売場に戻します。
そしてまた別の場所でもお客さんが、、、といういたちごっこを営業中繰り返します。結果、たたみ作業が間に合わずピークタイムには棚に陳列された服がぐちゃぐちゃに。。
つまりAの人にとっては経験上、売場が汚い、というのは
服の陳列が乱れている状態である。
との結論ありきで議論を行ってしまっています。それがAの人の議論を行うポジション、前提条件です。
一方、B、Cの人の店舗は服を全てハンガーに掛けて陳列するので服をたたむ事もないし、服の陳列が大きく乱れない事を経験している為、売場が汚く見える、というクレームの主原因は服の陳列の乱れだと捉えてはいません。
代わりに店舗内の老朽化した設備や店舗レイアウトに目が行き、トイレが汚れているだとか、お客さんが通る道に入荷商品を置きっぱなしにすれば、商品が買いづらくなる、また、お客さん心理を少しでも改善させるために、ピークタイム中にタイムセールを行う事で、お得感を出し、売場が乱れてもしょうがない!と思わせる。即ち別のサービスでお客さん心理を改善させる点に目が行きます。
三者の答えは対策として決して間違いではないけれども、間違いではないだけに、性質が悪いです。結論が見えてこないからです。
三者の前提がずれている、共有がされていないので相手の考えに共感できなかったり、何について話したかったのか分からなくなったり、結果冗長な話し合いになってしまった、というわけです。
2. 問題に対する背景が深堀りされず議論されている
3者の前提条件を擦り合わせしていな為、議論にズレが発生している事を上述しました。
その上、【ピークタイム中に店舗内が汚くて購買意欲が下がる】という問いを深堀りせずに、言いたいことを言い合うだけで最適な案を出すことが猶更困難になっています。
問題に対する背景を考えてみると、そもそも店舗内が汚い、という表現は具体性に欠けます。汚いとは何にが要因なのか?売り物が?お店の設備が?レイアウトが?何が汚い要因になっていると思うか?と仮説を立てることもなくいきなり経験を元に議論を開始してしまっています。
問題の背景もあやふやで、衣料店とだけ書いているが、個人経営の店なのか?チェーン店なのか?テナントに入ったお店なのか、単独店舗なのか。専門店なのか(レディース下着やスーツ)?衣料全般を扱っているお店か?背景によって考え方も変わってくるはずです。
もし、衣料店というのは実はレディース下着を販売しているお店なら子供が触るおもちゃのコーナーは重点的に手直しする。というアイディアは的を得てはいません。素早く畳む、というのも下着の専門店であれば適切な案とも言い難いかもしれません。基本ハンガー陳列なはず、、、です。あまり入ったことないので断言できませんが。。
ここから読み取れることは、一見全ての案が正しいと思っても、問題の背景を具体化、深堀すれば本筋と関係の無い事を話していることが見えてくる、ということです。
いやいや、問いには衣料店としか言ってないし、売場が汚いなんて色んな理由があるでしょ。後出しやんけ
そう思われるかもしれません。問題は、売場とかクレームとか置いておいて、常日頃、ビジネスに於いて抽象的な内容をトピックとし、報告物を作成したり、会議で議論をよく行っていないか?ということが上の問いは伝えたいのです。
この話はビジネスに限ったものではない。
こういった思考はビジネスだけに限ったものではなく、友人や夫婦やカップルの関係に置き換えても同じことは言えるのではないでしょうか。
例)彼女は旅行に行きたがっている。旅行の計画を立てたい。
彼氏:
彼女と一緒に行くならどこでもいいよ!(旅行では普段できない憩いの時間にしたい。)
彼女:
なんか一緒に遊べるところ行きたい。テーマパークなんていいかも!(旅行では普段とは違う刺激を求めたい。)
結果、色々遊べるプランをネットや雑誌を参考に考えるがなかなか決まらず。結局彼女の提案でディズニーランドに行くも、順番待ちに彼氏はくたくた、そんな彼氏の姿にイライラ、なかなか盛り上がらず。ホテルは彼氏、奮発して都内の外資系高級ホテルを予約。しかし彼女、どこか不満そう。。奮発したのに彼女はどこか不満そう。そう、彼女はミラコスタに泊まりたかったのである!って知らんがなー!
少々彼氏を悪役にしてしまいましたが、彼氏の前提【ゆっくりしたい】という前提条件は相手とすり合わせをおこなっているのでしょうか。
逆に彼女は普段と違う刺激を求めている、という前提条件があります。遊び方なんていくらでもあるけど、彼女の前提は旅行=アクティブに動く事、なのです。
この相反する前提条件を蔑ろにして旅行のプランを決める事は悲惨な結末が待ち受けている事は目に見えているのではないでしょうか。
また、旅行に行きたい背景も深堀り&具体化する必要があります。二人は付き合って間もない関係なのか?どれくらいの頻度で旅行に行っているのか?どのあたりに住んでいるのか?(関東?関西?九州?等々)遠距離恋愛なのか?近距離恋愛なのか?学生なのか?社会人なのか?等々。。
こんな小難しい事考えながら旅先を決める人間と旅行なんて行きたくない、というのが正直な答えですが。。
こちらはこういうつもりで言っているんだ、と思ってもその前提は相手に伝わっているとは限りません。なお性質が悪いのが所謂、【言わなくても分かるだろ!自分で考えろ!】と言っちゃうパターンです。いや、貴方の頭の中の前提なんて分かるわけないやろと。
前提条件をはっきりさせて論じる論法は演繹法と呼ばれる
演繹法(えんえきほう)は人間ごく自然に使っている論法です。
平たく言えば、一般的なルールや前提を元に、事象を観察し、結論を出す論法です。
三段論法とも言われます。先程のA、B、Cさんの考えを演繹法で表すと
Aさん
前提:商品は店員が畳んで陳列するもの。(一般的なルールに基づく)
↓
事象:売り場が汚いとクレームを受ける。
↓
結論:手直しの回数を増やす。
Bさん、Cさん
前提:商品はハンガーに掛けて陳列するもの。(一般的なルールに基づく)
↓
事象:売り場が汚いとクレームを受ける。
↓
結論:店舗レイアウトを見直す。クリンリネスを行う。
タイムセールを行い【汚いけどお得に買えたからしょうがない】、と思わせる。
双方の前提は一般的なルールに基づいたものではなかった為、話は当然平行線です。
万人が理解している前提
前提:サッカーではゴールキーパー以外手を使うと反則になる。(一般的なルールに基づく)
↓
事象:ディフェンダーが相手シュートを手で止めた
↓
結論:ディフェンダーは反則をとられた
上記のような【サッカーはゴールキーパー以外手を使うと反則になる。】というごく一般的な常識、ルールであれば、ディフェンダーがシュートを止めるため手を使って反則をとられた、という意見に対し、故意かどうか細かい部分は別として、大枠では異論を唱えることはさほど多くはないと思います。ルールでもあるし、一般的に知られているからです。
一方で前提条件が、一般的ではないものをチョイスしてしまうと、話の筋が通らなくなってしまいます。そうは言っても何でも間でも一般常識やルールなんてものを当てはめることはできないですし、人の経験や価値観によって前提はブレブレになってしまうと思います。
であれば尚更前提条件は擦り合わせを行うべきだと思います。
演繹法で論じる場合は本当に前提条件は一般的なルール、常識に基づくものなのかをよく考える、そして相手はその前提を理解してくれてるかを意識して議論を進めていくべきです。
まとめると
・双方の前提条件は必ずしも同じとは限らない
・故にコミュニケーションを行う際には前提条件のすり合わせを行う
・議論を行うべきトピックについて背景を具体化させ、深堀したうえで議論を開始する
・前提条件を元に事象に対し結論付ける論法は演繹法と呼ばれる
・演繹法を使うときは前提が本当に一般的な考えなのかを意識する。
最後に
一つテーマを書いて終わりにしたいと思います。
あなたの考える【優れたサッカー選手】とはどういう条件でしょうか?
あっ、優れた野球選手でもいいです。
これ!といった答えは当然ありません。解説はまた別の日記で書こうと思います。
10/24追記:
優れたサッカー選手について、下記ブログにて扱いました。